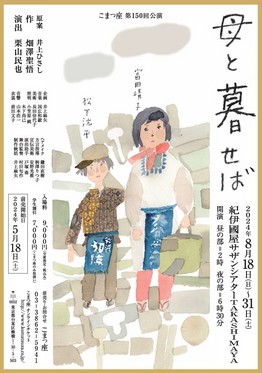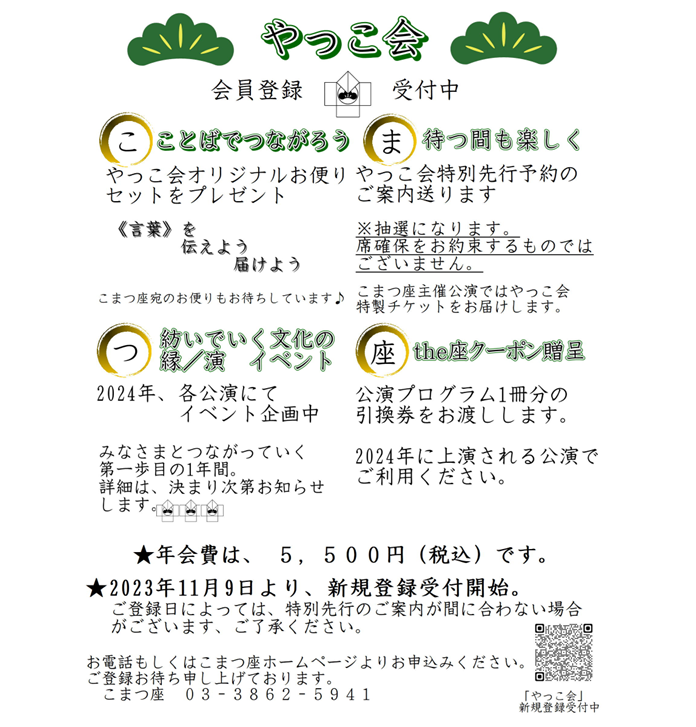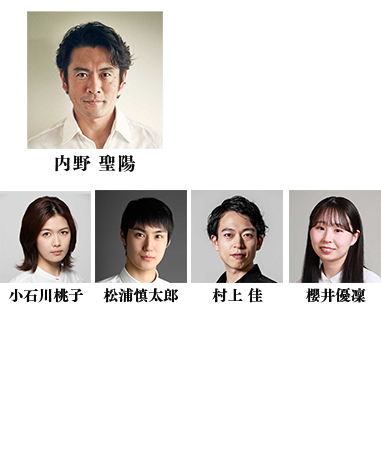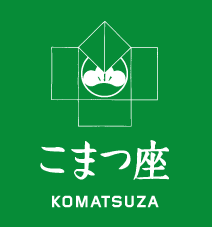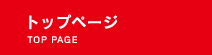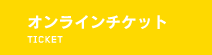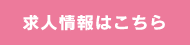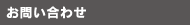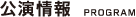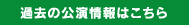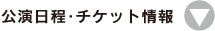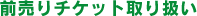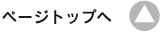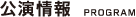
現在公演中の作品と今後公演予定の作品をご紹介いたします。
映画「木の上の軍隊」2025年上映決定
映画「木の上の軍隊」 2025年

実話をもとに描かれた
こまつ座戦後"命の"三部作第2作
初の映画化
映画「木の上の軍隊」
原案井上ひさし
沖縄出身平一紘監督
戦後80年2025年上映
こまつ座X
こまつ座Instagram
こまつ座『木の上の軍隊』
井上ひさしが書かなければならないとしてあげていた「ヒロシマ」「ナガサキ」「オキナワ」
その一つの「オキナワ」
大量の資料とメモをもとに
こまつ座代表井上麻矢が遺志を継ぎ、劇作家逢来竜太さん、演出家栗山民也さんと完成させ2013年に初上演。
再演、再再演を経て、2019年には沖縄でも上演。
世界からも注目される作品のひとつとなりました。
そして、
戦後80年2025年に初の映画化です。
詳細はまた後日発表いたします。
みなさま、お楽しみにしていてください☆
※システムの関係上
「チケットの購入はこちら」とありますが現在映画「木の上の軍隊」のチケット販売などは行っておりません。
映画「木の上の軍隊」 2025年
実話をもとに描かれた
こまつ座戦後"命の"三部作第2作
初の映画化
映画「木の上の軍隊」
原案井上ひさし
沖縄出身平一紘監督
戦後80年2025年上映
こまつ座『木の上の軍隊』
井上ひさしが書かなければならないとしてあげていた
「ヒロシマ」「ナガサキ」「オキナワ」
その一つの「オキナワ」
大量の資料とメモをもとに
こまつ座代表井上麻矢が遺志を継ぎ、劇作家逢来竜太さん、演出家栗山民也さんと完成させ2013年に初上演。
再演、再再演を経て、2019年には沖縄でも上演。
世界からも注目される作品のひとつとなりました。
そして、
戦後80年2025年に初の映画化です。
詳細はまた後日発表いたします。
みなさま、お楽しみにしていてください☆
※システムの関係上
「チケットの購入はこちら」とありますが現在映画「木の上の軍隊」のチケット販売などは行っておりません。
~


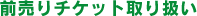
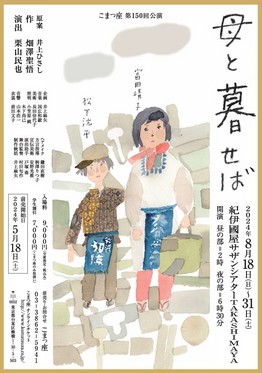

こまつ座 第150回公演 『母と暮せば』
作: 畑澤聖悟
演出:栗山民也
出演
富田靖子 松下洸平
☆コメント☆
畑澤聖悟さんからコメント☆
栗山民也さんからコメント☆
☆冨田靖子さんからコメント
☆松下洸平さんからコメント
《東京公演》
8月18日(日)〜31日(土)
紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA
こまつ座での一般発売の販売予定枚数は終了いたしました。
今後、キャンセル席や当日券の販売等も検討しております。
詳細はこまつ座HPやSNSにてお知らせいたしますので発表をお待ちください。
《全国公演》 7月、8月
●大阪公演 SKYシアターMBS
7月25日(木)15:30
7月26日(金)12:00/15:30
7月27日(土)12:00/15:30
7月28日(日)12:00/15:30
【主催】新歌舞伎座/MBSテレビ
【お問合せ】新歌舞伎座テレホン予約センター 06-7730-2222
●沖縄公演 糸満市観光文化交流拠点施設 シャボン玉石けんくくる糸満
※※チケット発売日6月18日(火)※※
8月3日(土) 13:00/17:00
8月4日(日) 13:00
【主催】琉球新報社
【お問合せ】琉球新報社 098‐865‐5255
「母と暮せば」沖縄公演 観劇スペシャルツアー
6月5日(水)10時発売
3日17時公演のチケット付き
公演後、出演者からの一言も予定
ツアーでは、映画「母と暮せば」の思い出の地をたどる 「#長崎追想 父・井上ひさしへの旅」(2023)特別上映会& #井上麻矢のトークショーも!
【ツアーお問い合わせ】
株式会社国際旅行社
https://its1.jp/travel_details/?tcode=YAG024
098-864-5931
https:///?tcode=YAG024●九州・演劇鑑賞会(会員登録制)
佐世保 アルカスSASEBO大ホール
8月7日(水)18:30
【お問合せ】佐世保市民劇場 0956-22-5294
佐賀 佐賀文化会館中ホール
8月8日(木)19:00
8月9日(金)13:00
【お問合せ】佐賀市民劇場 0952-26-0791
島原 島原文化会館
8月10日(土)18:30
【お問合せ】島原市民劇場 0957-63-3137
長崎 長崎市民会館文化ホール
8月11日(日)18:30
8月12日(月・祝)13:30
8月13日(火)12:00
【お問合せ】長崎市民劇場 095-823-6588
大村諫早 シーハットおおむら さくらホール
8月14日(水)14:00/18:00
【お問合せ】大村諫早市民劇場 0957-24-1015
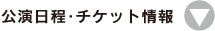
5月18日(土)
こまつ座 第150回公演 『母と暮せば』
作: 畑澤聖悟
演出:栗山民也
出演
富田靖子 松下洸平
《東京公演》
8月18日(日)〜31日(土)
紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA
《全国公演》
大阪公演 SKYシアターMBS
7月25日(木)15:30
7月26日(金)12:00/15:30
7月27日(土)12:00/15:30
7月28日(日)12:00/15:30
【主催】新歌舞伎座/MBSテレビ
【お問合せ】新歌舞伎座テレホン予約センター 06-7730-2222
沖縄公演 糸満市観光文化交流拠点施設 シャボン玉石けんくくる糸満
チケット発売日6月18日(火)
8月3日(土) 13:00/17:00
8月4日(日) 13:00
【主催】琉球新報社
【お問合せ】琉球新報社 098‐865‐5255
●九州・演劇鑑賞会(会員登録制)
佐世保 アルカスSASEBO大ホール
8月7日(水)18:30
【お問合せ】佐世保市民劇場 0956-22-5294
佐賀 佐賀文化会館中ホール
8月8日(木)19:00
8月9日(金)13:00
【お問合せ】佐賀市民劇場 0952-26-0791
島原 島原文化会館
8月10日(土)18:30
【お問合せ】島原市民劇場 0957-63-3137
長崎 長崎市民会館文化ホール
8月11日(日)18:30
8月12日(月・祝)13:30
8月13日(火)12:00
【お問合せ】長崎市民劇場 095-823-6588
大村諫早 シーハットおおむら さくらホール
8月14日(水)14:00/18:00
【お問合せ】大村諫早市民劇場 0957-24-1015

入場料 9,000円
学生割引 7,000円(こまつ座のみ取り扱い)
※全席指定・税込み

※上演時間:1時間30分予定(休憩なし)
※開場は開演の30分前です。

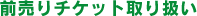
★販売&発券手数料無料★
こまつ座オンラインチケット
こまつ座 03-3862-5941
チケットぴあ
https://pia.jp/
イープラス
https://eplus.jp/komatsuza/(PC&スマホ)
※ファミリーマート店舗でも直接購入いただけます。
カンフェティ
0120-240-540(平日10:00〜18:00)
http://confetti-web.com/komatsuza
キノチケットカウンター
新宿東口・紀伊國屋書店新宿本店1階インフォメーションカウンター内(店頭販売 10:00〜18:30)
キノチケオンライン
https://store.kinokuniya.co.jp/ticket/
「やっこ会」はじまる
11月9日(木)新規会員登録開始
こまつ座は2024年度より、会員組織「やっこ会」を発足いたします。
☆ことばでつながろう
やっこ会オリジナルお便りセットをプレゼント
《言葉》を伝えよう届けよう
☆待つ間も楽しく
やっこ会特別先行予約のご案内を送ります。
※『母と暮せば』に関しましては、現時点では東京公演のみのお取り扱いを予定しております。
地方公演も先行を行うことが決まりましたら、随時ご案内いたします。
※抽選になります。
※席確保をお約束するものではございません。
☆紡いでいく文化の縁/演 イベント
2024年、各公演にてイベント企画中
みなさまとつながっていく第一歩目の1年間。
詳細は、決まり次第お知らせします。
☆the座クーポン贈呈
公演プログラム1冊分の引換券をお渡しします。
2024年に上演される公演でご利用ください。
★年会費は、 5,500円(税込)です。
★2023年11月9日より、新規登録受付開始。
ご登録日によっては、特別先行のご案内が間に合わない場合がございます。ご了承ください。
3月22日までにご入会いただいたお客様には、『母と暮せば』先行予約のご案内をお送りいたします。
お電話もしくはこまつ座ホームページよりお申込みください。
こまつ座 0338625941
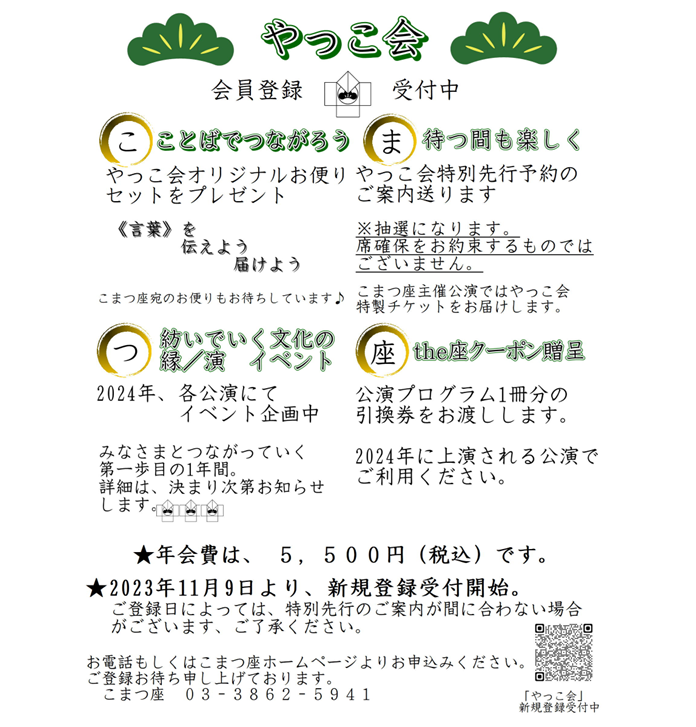
2024年井上ひさし生誕90年 第三弾
芭蕉通夜舟

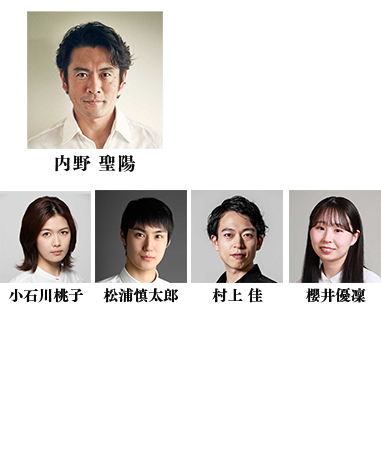
こまつ座 第151回公演『芭蕉通夜舟』
作: 井上ひさし
演出:鵜山仁
出演
内野聖陽
小石川桃子 松浦慎太郎 村上佳 櫻井優凜
《東京公演》
10月14日(月・祝)- 10月26日(土) 紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA
《全国公演》
◎群馬公演
【日時】10月29日(火) 18:30開演
【会場】高崎芸術劇場 スタジオシアター
【主催】高崎芸術劇場(公益財団法人 高崎財団)
【お問い合わせ】公益財団法人 高崎財団 TEL 027-321-7300
【入場料】6,000円(税込) U-25席:2,500円(税込)
【前売り開始】《Web先行》 7/26 (金)10:00 《電話》7/30(火)10:00 《窓口》7/31(水)10:00
◎宮城公演
【日時】11月2日(土)14:00開演
【会場】名取市文化会館 大ホール
【主催】ニイタカプラス 【共催】財団法人 名取市文化振興財団
【後援】宮城県教育委員会、名取市教育委員会、仙台文学館
【お問い合わせ】ニイタカプラス TEL 022-380-8251(平日9:30〜18:00)
【入場料】プレミアムシート:12,000円(税込) S席:9,500円(税込) A席:7,500円(税込) U-25席:5,000円(税込)
【前売り開始】7/5 (金)10:00
◎岩手公演
【日時】11月12日(火)19:00開演
【会場】盛岡劇場 メインホール
【主催】公益財団法人 盛岡市文化振興事業団
【お問い合わせ】 盛岡劇場 TEL 019-622-2258
【入場料】一般:5,000円(税込) U-25チケット:2,000円(税込)(当日各500円増)
【前売り開始】8/29 (木)
◎兵庫公演
【日時】11月16日(土)13:00開演
【会場】兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホール
【主催】兵庫県、兵庫県立芸術文化センター
【お問い合わせ】芸術文化センターチケットオフィス TEL 0798-68-0255
【入場料】一般:7,000円(税込)
【前売り開始】8/3(土)
◎丹波篠山公演
【日時】11月17日(日)15:00開演
【会場】田園交響ホール
【主催】丹波篠山市・丹波篠山市教育委員会
【お問い合わせ】丹波篠山市立 田園交響ホール TEL 079-552-3600
【入場料】一般:4,500円(税込) 友の会/グループ割:4,000円(税込)
【前売り開始】9/14 (土)9:00
◎名古屋公演
【日時】11月23日(土)17:00開演、24日(日)12:00開演/16:00開演
【会場】ウインクあいち 大ホール
【主催】メ〜テレ/メ〜テレ事業
【お問い合わせ】メ〜テレ事業 TEL 052-331-9966
【入場料】全席指定:9,000円(税込)※未就学児入場不可
車いす席:9,000円(税込)、U-25:4,500円(税込)
※車いす席、U-25はメ〜チケ(車いす席は電話のみ)にて一般発売より取り扱い
※U-25は、観劇時25歳以下対象(当日指定席券引換・座席数限定・要本人確認書類)
【前売り開始】8/17 (土)10:00
◎大阪公演
【日時】11月30日(土)14:00開演
【会場】枚方市総合文化芸術センター 関西医大 小ホール
【主催】枚方市総合文化芸術センター指定管理者 アートシティひらかた共同事業体
【お問い合わせ】枚方市総合文化芸術センター TEL 072-845-4910
【入場料】全席指定:7,000円(税込) 全席指定(注釈付):7,000円(税込)
※注釈付席は機材席前のお席になるため、鑑賞中機材音が気になる場合があります。予めご了承ください。
【前売り開始】会員先行 8/10 (土) 一般(電話・WEB)8/21(水) 窓口 8/22(木)※残席がある場合※各日10:00より発売
★演出・鵜山仁さんコメント
『奥の細道』の序文には、「月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人也」とあります。芭蕉は旅する、ハイクする、というのが通り相場ですが、この旅は、おそらく人間の一生の射程を超えて、月日とともにどこまでも、銀河の果てまでつながって行くはずだと思います。
そんな旅の道案内となるべく、アートがどんな役割を果たせるか、これがやはりわれわれにとっては、大きな関心事です。
今回、内野芭蕉が、40年来の旅のタスキを受け継いで、悠久の旅路の船頭をつとめます。
★内野聖陽さんコメント
またも一人芝居。いえ、ほぼ一人芝居。前回の『化粧二題』では、見えない透明の劇団員たちが居て、一人で演じていても孤独感はありませんでした。でも今回は『人は独りで生き、独りで死んでいくより他に道は無い』ことを極めるために苦吟した芭蕉さんです。聞いただけでも凄まじい人生!尻込みしそうです。しかし、役者というのも孤独なお仕事です。この作品を読んだときとても共感するメッセージが込められていると感じました。ほぼ一人で芭蕉の人生を背負うのは怖いけれど、井上ひさし先生の言葉の力、鵜山仁さんの熟練の演出、そして黒子役の若い共演者と共に、芭蕉の人生に食らいついて、挑みかかって、俳諧で道を究めた芭蕉の人生をあぶり出したいと思っております。
面白いことを深く、そして愉快に、そして真剣に、表現していきたいと、期待と恐怖ないまぜの状態の裏で、私の闘志はひそかに育ち始めております。
どうぞご期待ください。
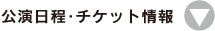
8月3日(土)
こまつ座 第151回公演『芭蕉通夜舟』
作: 井上ひさし
演出:鵜山仁
出演
内野聖陽
小石川桃子 松浦慎太郎 村上佳 櫻井優凜
《東京公演》
10月14日(月・祝)- 10月26日(土) 紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA
《全国公演》
◎群馬公演
【日時】10月29日(火)18:30開演
【会場】高崎芸術劇場 スタジオシアター
【主催】高崎芸術劇場(公益財団法人 高崎財団)
【お問い合わせ】公益財団法人 高崎財団 TEL 027-321-7300
【入場料】6,000円(税込) U-25席:2,500円(税込)
【前売り開始】《Web先行》 7/26 (金)10:00 《電話》7/30(火)10:00 《窓口》7/31(水)10:00
◎宮城公演
【日時】11月2日(土)14:00開演
【会場】名取市文化会館 大ホール
【主催】ニイタカプラス 【共催】財団法人 名取市文化振興財団
【後援】宮城県教育委員会、名取市教育委員会、仙台文学館
【お問い合わせ】ニイタカプラス TEL 022-380-8251(平日9:30〜18:00)
【入場料】プレミアムシート:12,000円(税込) S席:9,500円(税込) A席:7,500円(税込) U-25席:5,000円(税込)
【前売り開始】7/5 (金)10:00
◎岩手公演
【日時】11月12日(火)19:00開演
【会場】盛岡劇場 メインホール
【主催】公益財団法人 盛岡市文化振興事業団
【お問い合わせ】 盛岡劇場 TEL 019-622-2258
【入場料】一般:5,000円(税込) U-25チケット:2,000円(税込)(当日各500円増)
【前売り開始】8/29 (木)
◎兵庫公演
【日時】11月16日(土)13:00開演
【会場】兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホール
【主催】兵庫県、兵庫県立芸術文化センター
【お問い合わせ】芸術文化センターチケットオフィス TEL 0798-68-0255
【入場料】一般:7,000円(税込)
【前売り開始】8/3(土)
◎丹波篠山公演
【日時】11月17日(日)15:00開演
【会場】田園交響ホール
【主催】丹波篠山市・丹波篠山市教育委員会
【お問い合わせ】丹波篠山市立 田園交響ホール TEL 079-552-3600
【入場料】一般:4,500円(税込) 友の会/グループ割:4,000円(税込)
【前売り開始】9/14 (土)9:00
◎名古屋公演
【日時】11月23日(土)17:00開演、24日(日)12:00開演/16:00開演
【会場】ウインクあいち 大ホール
【主催】メ〜テレ/メ〜テレ事業
【お問い合わせ】メ〜テレ事業 TEL 052-331-9966
【入場料】全席指定:9,000円(税込)※未就学児入場不可
車いす席:9,000円(税込)、U-25:4,500円(税込)
※車いす席、U-25はメ〜チケ(車いす席は電話のみ)にて一般発売より取り扱い
※U-25は、観劇時25歳以下対象(当日指定席券引換・座席数限定・要本人確認書類)
◎大阪公演
【日時】11月30日(土)14:00開演
【会場】枚方市総合文化芸術センター 関西医大 小ホール
【主催】枚方市総合文化芸術センター指定管理者 アートシティひらかた共同事業体
【お問い合わせ】枚方市総合文化芸術センター TEL 072-845-4910
【入場料】全席指定:7,000円(税込) 全席指定(注釈付):7,000円(税込)
※注釈付席は機材席前のお席になるため、鑑賞中機材音が気になる場合があります。予めご了承ください。
【前売り開始】会員先行 8/10 (土) 一般(電話・WEB)8/21(水) 窓口 8/22(木)※残席がある場合※各日10:00より発売

入場料 8,500円
U-30(観劇時30歳以下) 6,000円
高校生以下(こまつ座のみ扱い) 2,000円
※全席指定・税込み

※上演時間:1時間30分予定
※当日券:開演の1時間前に劇場入口にて発売いたします。
※開場は開演の30分前です。

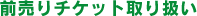
★販売&発券手数料無料★
こまつ座オンラインチケット
こまつ座 03-3862-5941
チケットスペース
03-3234-9999(10:00〜15:00※休業日除く)
http://www.ints.co.jp/
チケットぴあ
https://pia.jp/(PC&スマホ)
※セブン-イレブン店頭でも直接購入いただけます。
ローソンチケット
https://l-tike.com/(Lコード:31818 PC&携帯)
※ローソン・ミニストップ店内Loppiで直接購入いただけます。
イープラス
https://eplus.jp/komatsuza/(PC&スマホ)
※ファミリーマート店舗でも直接購入いただけます。
カンフェティ
0120-240-540(平日10:00〜18:00)
http://confetti-web.com/komatsuza
キノチケットカウンター
新宿東口・紀伊國屋書店新宿本店1階インフォメーションカウンター内(店頭販売 10:00〜18:30)
キノチケオンライン
https://store.kinokuniya.co.jp/ticket/
2024年井上ひさし生誕90年 第四弾
太鼓たたいて笛ふいて


こまつ座 第152回公演『太鼓たたいて笛ふいて』
作: 井上ひさし
演出:栗山民也
出演
大竹しのぶ 高田聖子 近藤公園 土屋佑壱 天野はな 福井晶一 朴勝哲
≪東京公演≫
11月1日(金) ー 30日(土) 紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA
≪全国公演≫
■大阪公演 新歌舞伎座
12月4日(水) 12:00
12月5日(木) 12:00
12月6日(金) 12:00
12月7日(土) 12:00/17:00
12月8日(日) 12:00
■愛知公演 ウインクあいち
■福岡公演 キャナルシティ劇場
■山形公演 やまぎん県民ホール
12月25日(水) 15:00
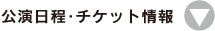
9月7日(土)
こまつ座 第152回公演『太鼓たたいて笛ふいて』
作: 井上ひさし
演出:栗山民也
出演
大竹しのぶ 高田聖子 近藤公園 土屋佑壱 天野はな 福井晶一 朴勝哲
≪東京公演≫
11月1日(金)ー 30日(土) 紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA
☆★スペシャルトークショー★☆
☆11月 7日(木)1時公演後
☆11月13日(水)1時公演後
☆11月20日(水)1時公演後
※トークショーは、開催日以外の『太鼓たたいて笛ふいて』のチケットをお持ちの方でもご入場いただけます。
※出演者は都合により変更の可能性がございます。
≪全国公演≫
■大阪公演 新歌舞伎座
12月4日(水) 12:00
12月5日(木) 12:00
12月6日(金) 12:00
12月7日(土) 12:00/17:00
12月8日(日) 12:00
■愛知公演 ウインクあいち
■福岡公演 キャナルシティ劇場
■山形公演 やまぎん県民ホール
12月25日(水) 15:00

入場料 10,500円
U-30(観劇時30歳以下) 6,500円
高校生以下(こまつ座のみ扱い) 3,000円
※全席指定・税込み

※上演時間:2時間45分予定(休憩含む)
※当日券:開演の1時間前に劇場入口にて発売いたします。
※開場は開演の30分前です。
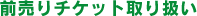
こまつ座オンラインチケット
こまつ座 03-3862-5941
チケットスペース
03-3234-9999(10:00〜15:00※休業日除く)
http://www.ints.co.jp/
チケットぴあ
https://pia.jp/(PC&スマホ)
※セブン-イレブン店頭でも直接購入いただけます。
ローソンチケット
https://l-tike.com/(Lコード:31917 PC&携帯)
※ローソン・ミニストップ店内Loppiで直接購入いただけます。
イープラス
https://eplus.jp/komatsuza/(PC&スマホ)
※ファミリーマート店舗でも直接購入いただけます。
カンフェティ
0120-240-540(平日10:00〜18:00)
http://confetti-web.com/@/komatsuza
キノチケットカウンター
新宿東口・紀伊國屋書店新宿本店1階インフォメーションカウンター内(店頭販売 10:00〜18:30)
キノチケオンライン
https://store.kinokuniya.co.jp/ticket/